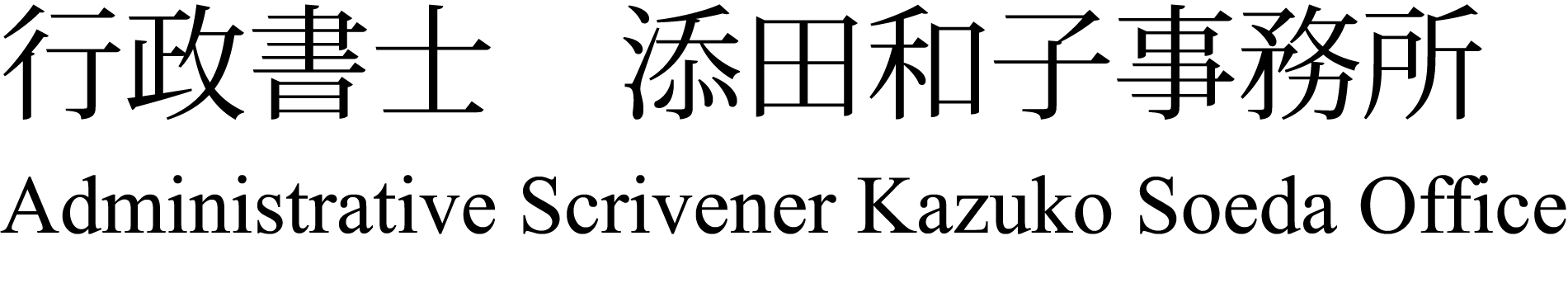民泊を始めたい!③180日ルールとは?
今回は、民泊を始めるための第3回目の記事になります。
民泊を始めるにあたっては、法律上のルールや自治体ごとの条例など、事前に知っておくべきポイントがいくつもあります。なかでも、「180日ルール」は、民泊の運営において特に注意が必要な制度です。
この記事では、民泊新法(住宅宿泊事業法)に基づく180日ルールの概要とその意味、さらに他の制度との違いについて、わかりやすく解説します。
■ 民泊とは? 住宅宿泊事業法の登場
民泊について簡単におさらいです。「民泊」とは、旅館業の許可を取らずに、自宅などの住宅を活用して宿泊サービスを提供する形態をいいます。以前はグレーゾーンとされていましたが、2018年6月に「住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)」が施行され、一定の条件を満たせば合法的に民泊を行えるようになりました。
住宅宿泊事業法に基づいて民泊を運営するには、都道府県などへの届出が必要です。届出制なので、旅館業法による営業許可と比べると手続きは簡易ですが、その代わりに「180日ルール」など、いくつかの制限があります。
■ 「180日ルール」とは?
住宅宿泊事業法に基づく民泊では、年間の宿泊提供日数が180日以内に制限されています。つまり、1年間のうち実際に宿泊者を受け入れられるのは最大180日までということです。
◎ 宿泊日数のカウント方法
宿泊日数は、1部屋1泊を1日としてカウントされます。複数の宿泊者が同じ日に泊まっても「1日」と数えます。また、チェックイン・チェックアウトの時刻に関係なく、その日に宿泊者がいたかどうかでカウントされます。
■ なぜ180日という制限があるの?
この制限は、地域住民の生活環境を保護するために設けられたものです。特に都市部では、近隣住民とのトラブル(騒音、ゴミ出しの問題など)が問題視されていました。そのため、「住宅としての機能を守る」観点から、年間の営業日数に上限が設けられたのです。
■ 180日以上営業したい場合には?
180日以上の営業を希望する場合は、旅館業法に基づく許可を取得する必要があります。具体的には、「簡易宿所営業」という形態での許可申請が一般的です。
旅館業法での運営は、180日の制限がない代わりに、下記のようなより厳しい条件をクリアする必要があります。
-
客室の面積基準
-
避難経路や消火設備などの消防基準
-
管理者の常駐やフロント設置の要件(自治体によって異なる)
■ 特区民泊や条例による例外
180日ルールは住宅宿泊事業法による民泊に限った制限ですが、地域によっては特区民泊や独自条例による民泊制度を活用することもできます。
◎ 特区民泊(国家戦略特区)
たとえば東京都大田区や大阪市などでは、「特区民泊」として、旅館業法に代わる特例制度が設けられており、一定条件のもとで最短2泊3日からの営業が可能です。180日制限もありません。
◎ 条例による追加制限
一方で、自治体によっては、住宅宿泊事業法に基づく民泊に対してさらに厳しい制限を設けているところもあります。たとえば、
学校周辺では平日の営業を禁止・営業可能日を週末のみに限定・管理者の居住を必須とする
といった内容です。民泊を始める前には、必ず自分の地域の条例を確認するようにしましょう。
■ 民泊運営に必要な準備
180日ルールを理解した上で、住宅宿泊事業を始めるには以下のような準備が必要です。
-
管轄自治体への届出
-
住宅の適正な改修(火災報知器の設置、施錠設備など)
-
近隣住民への事前説明
-
管理業務の体制(自主管理または管理業者の委託)
特に初めての方は、行政書士など専門家に相談することで、スムーズな手続きと法令遵守が可能になります。
■ まとめ|180日ルールを正しく理解して民泊を始めよう!
民泊は、空き部屋を活用できる魅力的なビジネスですが、「180日ルール」という明確な制限があることを忘れてはいけません。住宅宿泊事業法で運営する場合は、その枠内で収益計画を立てる必要がありますし、それ以上の営業を希望する場合は、旅館業法の許可取得も検討する必要があります。
自分の目的や地域の状況に合わせて、どの制度を選ぶのかをしっかり考え、トラブルのない安全な民泊運営を目指しましょう。