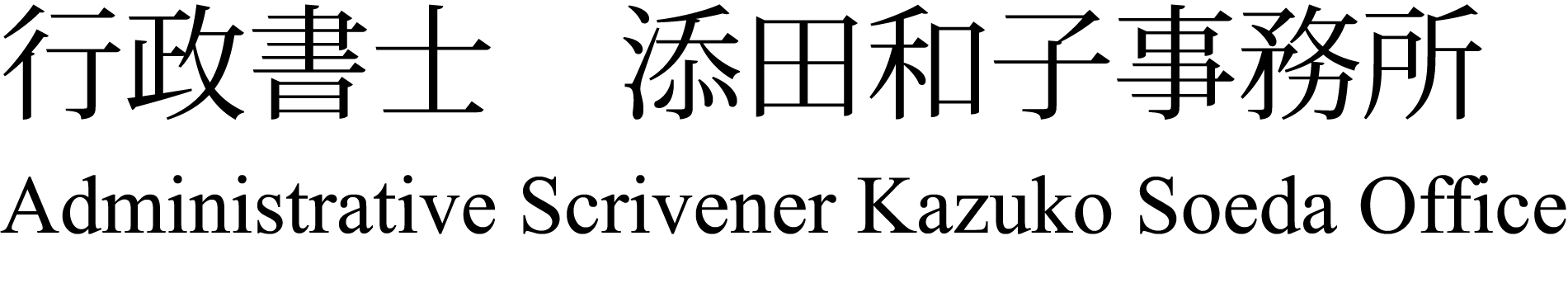【安全対策の要】民泊事業者必見!非常用照明器具の設置基準と重要性
住宅宿泊事業(民泊)では、宿泊者の安全確保が最も重要です。特に夜間や災害時に停電が起こった場合、避難経路を確保するために非常用照明器具の設置が義務付けられています。
ここでは、法律の根拠や設置が必要なケース、設置するときのポイントをわかりやすくまとめます。
1. 非常用照明器具とは?
火災・地震・停電などの非常時に、自動的に非常電源に切り替わって明かりを確保する照明設備です。
避難経路や室内を照らすことで、安全に外へ避難できるようにする役割があります。
2. 法的な根拠
非常用照明器具の設置は、
-
住宅宿泊事業法
-
国土交通省告示第1109号
-
建築基準法施行令第126条の5
などで定められています。
民泊事業者(届出者)は、火災・災害時に宿泊者の安全を確保するため、
-
非常用照明器具
-
避難経路の表示
-
その他の安全対策
を講じなければならないとされています。
3. 設置が必要かどうかの判断基準
■ 設置が不要な場合(全体免除)
次の 両方 を満たす住宅は、非常用照明器具の設置が不要です。
-
宿泊室の合計床面積が 50㎡以下
-
家主が 不在にならない(同居型民泊)
つまり、「家主が一緒に住んでいて、広くない住宅」であれば、設置義務はありません。
■ 設置が必要な場合
次のいずれかに該当すると、原則として設置が必要です。
-
家主が不在となる住宅(いわゆる「家主不在型民泊」)
-
宿泊室の床面積が 50㎡を超える 住宅
4. 一部の部屋で設置が不要になるケース(個別免除)
住宅全体では設置が必要でも、次の条件を満たす居室には設置不要となります。
-
避難階またはその直上・直下階で、
・採光に有効な窓面積が床面積の1/20以上
・出口までの歩行距離が(避難階で30m以内/上下階で20m以内) -
床面積30㎡以下で、地上に直接出られる出口がある部屋
-
床面積30㎡以下で、
・非常用照明が設けられている、または
・外気に面して採光が取れている部屋
また、クローゼット・洗面所・浴室などは宿泊室や避難経路ではないため、設置は不要です。
5. 技術基準と図面への記載ポイント
非常用照明器具を設置する場合は、建築基準法施行令第126条の5 の構造基準に適合している必要があります。
たとえば、
-
停電時に自動で非常電源へ切り替わる
-
耐熱性のある電球・配線を使用している
などの条件を満たす必要があります。
製品を選ぶ際は、
(一社)日本照明工業会(JLMA)の「JIL適合マーク」 があるものを選ぶと安心です。
また、届出時の図面には以下を明示します:
| 記載内容 | 説明 |
|---|---|
| 非常用照明器具の位置 | 設置場所を明記 |
| 予備電源の種類と位置 | 非常電源の設置状況 |
| 照度の範囲 | 床面で1ルクス以上確保できる範囲 |
| 構造詳細 | 器具の材質・形状など |
6. 消防法上の誘導灯との関係
消防法では、避難経路を示すために誘導灯の設置が求められる場合があります。
ただし、共同住宅などで誘導灯が免除される場合でも、停電時に避難経路を明るくできるように非常用照明器具や携帯用照明器具の設置が必要になります。
まとめ
-
民泊では、宿泊者の安全確保のため非常用照明器具が重要。
-
家主同居・50㎡以下なら原則不要だが、それ以外は設置が必要。
-
設置基準は建築基準法・住宅宿泊事業法に基づく。
-
図面には照明位置や構造を明記する必要がある。
非常用照明器具の設置は、宿泊者の命を守る最も基本的な安全対策です。
不明な点がある場合は、事前に自治体の建築指導課や消防署へ確認しましょう。